|
リスク管理

解答 3
選択肢1、2については記述の通り。特に説明は必要ないでしょう。変額個人年金保険の支払い保険料は、生命保険料控除の対象となることだけはついでに覚えておいてくださいね。
無選択型保険とは、記述にあるとおり、告知・診査が不要ですが、保険料は高くなります。保険会社からしたら保険金の支払いリスクが高くなるわけですから、もらう分はしっかりもらわないとつぶれてしまいますよ。ですから、選択肢3が誤りの記述となります。
終身払いと有期払いでは、記述にあるとおり「毎回の」保険料は終身払いのほうが安くなります。「支払い総額」は、終身払いのほうが多くなりますからね。保険にこだわる必要はありません。理屈をおぼえておきましょう。
必要な金額(仮に1000万円)を10年で返済する場合と20年で返済する場合では、「毎回の」支払い金額は20年で返済するほうが少なくなりますね。でも、通常利子というものが取られますから、返済期間が長いと「支払い総額」は多くなるということです。

解答 4
文章がややこしく書いてありますが、内容的には正解したい問題です。どの科目でもこの問題のように税務に関する問題は出題されますから、税金だけはきっちりチェックするくせをつけておきましょう。
まず、正解肢(誤りの記述)である4番の記述。これは、相続税の対象ですね。一時所得となるのは「自分で払って自分でもらう」パターンの場合。保険料負担者は夫で妻が相続したのですから、一時所得となるはずはありません。ですから、これが誤りの記述となります。
個人年金保険料控除の対象となるのは、以下の4つの条件を満たし、かつ個人年金保険料税制適格特約を付加した場合です。
・年金受取人が契約者またはその配偶者
・年金受取人は被保険者と同一人物
・保険料払込期間が10年以上(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始が60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上。
選択肢1の場合は、「年金受取人は被保険者と同一人物」という条件を満たしていませんね。ですから、一般の生命保険料控除の対象となります。
選択肢2については、基本中の基本です。夫が死亡したことにより受け取る保険金ですから、相続税の対象となります。
選択肢3の記述については、「年金受け取り開始時に」という部分は特に意識して覚えておきましょう。時折、ひっかけ問題の対象に部分になります。

解答 4
個人年金保険に関する問題ですね。ここは、問題文の記述のみならずもう少し覚えておいたほうが良いでしょう。個人年金保険の扱いについては、終身年金、有期年金、確定年金の扱いぐらいは最低限覚えておいてくださいね。特に、年金の支払われ方の違いは要チェックです。詳しくは、「2級FP技能士無料ポイント講座 第4回 個人年金保険の種類」を参照してください。
保証期間付き有期年金では、一定の保証期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われ、保証期間中に被保険者が死亡した場合には、遺族が期間満了まで年金をうけとるまたは、一時金でうけとるのどちらかを選択することになります。保証期間終了後は、被保険者が生存しており、かつ年金支払い期間中である場合に限り、年金が支払われます。つまり、保証期間が終了した後は、通常の有期年金と同じ扱いということです。
確定年金では、年金支給開始後、定められた一定期間中、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われます。被保険者が一定期間中に死亡した場合には、遺族が期間満了まで年金をうけとるまたは、一時金でうけとるのどちらかを選択することになります。一定の年金支払い期間が終了すると年金の支払いは終了します。
一時払い変額個人年金については記述の通りです。一時払い変額個人年金は、5年以内の満期または、解約の場合は、受け取り金額と払い込み保険料との差益に対して20%の分離課税(金融類似商品扱い)になることもあわせて覚えておきましょう。
夫婦年金は、夫婦のいずれかが生きている限り年金を受け取り続けることのできる年金保険ですが、夫婦ともに生きている場合と片方のみ生きている場合の受け取る年金額の取り扱いについては商品ごとに異なります。ですから、この記述のように断定することはできません。

解答 2
生命保険料控除についての問題です。正解肢である(誤りの記述)である2番については、このまま覚えておきましょう。
詳細については「2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜 第14回 生命保険料控除とは?」および「〜リスク管理〜第7回 生命保険と個人年金保険料控除」を参照してください。ここは、試験対策上、非常に重要な箇所ですから、絶対に間違えてはいけません。

解答 2
法人契約の経理処理に関する問題です。法人契約の経理処理については、深くやりこもうとすると非常に大変なのですが、最低限、経理処理の基本、養老保険のハーフタックスプランの場合の経理処理、長期平準保険の経理処理ついては目を通しておきましょう。詳細については、2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜第10回から第12回に掲載してあります。
Aのガン保険の場合は、終身払い込みで死亡保険金がないとなっていますから、この条件であれば、保険料の全額を損金とすることが出来ます。あくまで、「この条件であれば」ですからね。試験対策的には、ここまでの知識が要求されることは少ないと思いますから、余裕のある方のみ覚えておいてください。
Bの保険については、ハーフタックスプランの経理処理となりますから、養老保険の支払い保険料(特約保険料はのぞく)の1/2は資産計上、1/2は損金計上とされます。したがって、選択肢2は誤りの記述となります。
Cの個人年金保険については、死亡給付金受取人が役員・従業員の遺族・年金受取人が法人となっている場合は保険料のうち、9/10は年金積立金として資産計上、1/10は、福利厚生費として損金計上とされます。ただし、被保険者が特定の者のみとなっている場合は、福利厚生費とはならず、給与・報酬として扱われます。また、死亡給付金受取人・年金受取人がともに法人である場合は、保険料の全額が資産計上(特約保険料はのぞく)、死亡給付金受取人・年金受取人がともに役員・従業員である場合は、保険料の全額(特約保険料はのぞく)が給与・報酬として扱われます。

解答 3
民間の自動車保険については、対人賠償保険、対物賠償保険、自損事故保険、無保険者傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険の6つの保険が基本となっており、これは覚えておくしかありません。概要だけは目を通しておくようにしましょう。正解肢となっている3番の記述(誤りの記述)では、長男に対する損害を補償するとしている点が誤りです。対物賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。

解答 1
損害賠償金に関する問題です。保険ではなく完全に税金に関する問題。FP試験では、税金に関する知識がとても大事だと再認識してくださいね。と言いつつ、この問題は試験テクニックで正解できたりして・・・。
選択肢1と2をよく見比べてみましょう。同じようなことが書いてありますね。このようなパターンの出題では、どちらかが間違いであることがよくあります。問題を読んでよくわからない場合でも正解することをすぐにあきらめてはいけません。
この2つの記述を見比べると1番の記述は・・・・・。ケガの場合は、非課税なのに死亡の場合は相続税の課税対象なんておかしくありませんか?
というわけで、この問題に関しては知らなくても正解することができます。ただし、最初に申し上げたようにFP試験では、税金に関する知識がとても大事です。問題にはなっていませんが、商品の損害に対する損害保険金は課税対象(個人なら所得税の課税対象)となることもおさえておいてくださいね。

解答 3
特約とがん保険に関する問題です。この問題は、簡単そうに見えますが、保険業界以外の方にとっては難しい問題ですね。間違えてしまっても落ち込む必要はありません。このあたりの知識を完全に網羅しようとすると時間がかかりますから、試験前にざっと目を通しておくように心がけましょう。
選択肢1、4については、特に説明は必要ないと思いますから割愛します。
選択肢2については、がん保険には、記述の通り、入院給付金の支払い日数に制限はありません。プラスアルファの知識として、がん保険では、責任開始日から90日等の免責期間が設けられていることもあわせて覚えておいてくださいね。
選択肢3は誤りの記述(正解肢)です。障害給付金は、不慮の事故で所定の障害状態になった場合に障害状態に応じた金額が支払われます。「病気」と言う部分が間違いですね。

解答 2
介護保険に関する問題ですが、正解を選ぶだけなら常識で正解できる問題です。こういう問題はあてるだけはあててくださいね。民間の介護保険加入年齢が40歳以上なわけがありません。これでは、保険金を支払う可能性のある時期が近い分、儲かりませんからね。
では、正解肢がわかったところで、その他の選択肢について説明します。まず、選択肢1の記述については、この文章そのまま覚えておいてください。良く出てきます。珍しく親切に現物給付(各種サービスの提供)としてありますが、()の記述がなくても現物給付=サービスの提供だと理解できるようにしておいてください。
選択肢3は、特に説明は必要はないと思うのですが、選択肢4については少し注意してください。この記述は正しい記述ですが、民間の介護保険では、公的介護保険の認定と完全に一致させているわけではありません。断定的な表現となっているような場合は誤りの記述となります。

解答 4
リスク管理と損害保険に関する問題ですが・・・・またまた常識で正解できてしまう問題です。毎回こんな問題ばかり出題されるわけではありませんから、誤解しないようにしてくださいね。
バイクで事故をおこして個人賠償責任保険って・・・そんなわけないでしょ!
原動機付き自転車であっても車と同様に自賠責保険は強制加入となっていますし、任意の民間保険(バイク保険等)も当然存在します。ですから選択肢4の記述は誤りです。
では、正解肢がわかったところで、その他の選択肢について説明します。
人身傷害補償保険では、過失割合に関係なく運転者や同乗者等の死傷、後遺障害について保険金が支払われます。搭乗者傷害保険に比べて保険料は割高となりますが、補償内容は、人身傷害補償保険のほうがかなり広くなっています。
価格協定特約とは、保険価額を時価でなく再調達価額(もう一度同じものを得るために必要となる金額のこと)で決める特約のことです。所得税のところで減価償却って学習しましたよね。時間の経過とともに建物は価値が減少していってしまいますから、古い家ですと時価を基準に保険価額を決めても十分な保障が得られません。ですから、火災保険ではこのような特約が用意されているのです。
所得保障保険の内容については記述の通りですが、プラスアルファの知識として所得保障保険の支払い保険料は、生命保険料控除の対象となることもあわせて覚えておきましょう。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
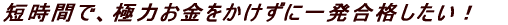
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 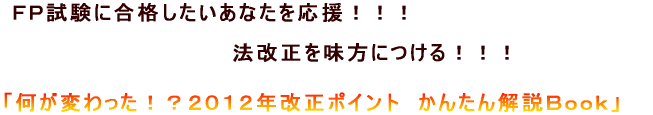
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 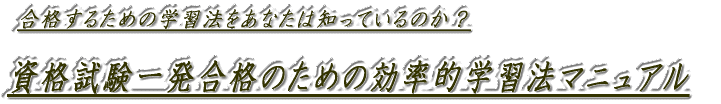
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 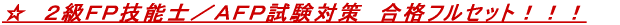 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| 

![]()
