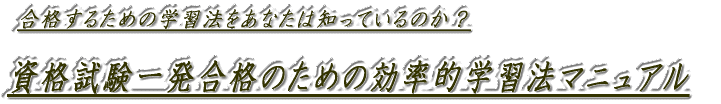タックスプランニング

解答 3
所得税の原則的な仕組みに関する問題です。かなり基本的な問題ですね。これは、絶対に正解しなければいけません。間違えてしまった方は、所得税の速算表を思い出しましょう。所得に応じて税率が異なっていたはずですよ!所得税の税率は、所得が多いほど高い税率が課せられるようになっているのです。これを超過累進税率といいます。問題にはなっていませんが、名前も覚えておきましょう。
● 参考 所得税の速算表
| 課税される所得金額 (千円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 195万円以下 |
5% |
0円 |
| 195万円超〜330万円以下 |
10% |
97500円 |
| 330万円超〜695万円以下 |
20% |
427500円 |
| 695万円超〜900万円以下 |
23% |
636000円 |
| 900万円超〜1800万円以下 |
33% |
1536000円 |
| 1800万円超 |
40% |
2796000円 |

解答 4
国内株式からうける配当所得に関する問題です。先ほどとは打って変わって、細かい点を聞いてきますね。非上場株式の配当については、少額配当であれば、確定申告不要とすることができます。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢4番となります。FP試験対策としては、選択肢1の配当所得の計算式、特に負債利子の金額を控除できる点はおさえておいたほうがよいと思いますよ。
● 参考 少額配当
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下であるものをいいます。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)/12

解答 3
損益通算後の総所得金額を求める問題です。おっと!2級FP技能士無料ポイント講座で取り上げている不動産所得の注意点がそのまま出題されていますね!この問題は、このサイトを見ている方はぜひ、正解してくださいよ!
損益通算をおこなうことのできる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得ですが、それぞれ、ちょっとずつ注意点があるのです。不動産所得の場合は、不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できません。したがって、通算できるのは、▲200万円ではなくて、▲175万円。一時所得の赤字は通算できませんから、総所得金額は、
550万円−175万円+75万円 = 450万円
となります。この問題は、FP試験において、よく出題されるパターンのひとつ。これから、FP試験を受験される方は、必ずできるようになっておいてくださいね!
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第6回 不動産所得とは?

解答 2
所得税の所得控除に関する問題です。消去法ですね。いや、寡婦控除をしっかりおさえていた方は、もちろん立派ですが、この問題の誤りの記述は、どれも代表的な所得控除の代表的なお話ですから、自信をもって、1、3、4は違う!と言っていただきたいところです。間違えてしまった方は、必ずよく復習しておくようにしてくださいね。
選択肢1 誤りの記述です。医療費控除の計算式は、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)ですよ。一律10万円ではありません。
選択肢2 正しい記述です。
選択肢3 誤りの記述です。「納税者の合計所得金額が1000万円以下であること」が条件になるのは、配偶者特別控除です。配偶者控除には、この要件はありませんよ。
選択肢4 誤りの記述です。扶養親族が、特定扶養親族に該当する場合や老人に該当する場合は、控除額は異なりますよ。かなり基本的なお話ですから、これだけは絶対に選んではいけない記述です。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第12回 扶養控除とは?
第13回 社会保険料控除とは?医療費控除とは?

解答 2
所得税の源泉徴収に関する問題です。一瞬、源泉徴収で4択???とびっくりしてしまいましたが、やられましたね。これは知っていて間違えてしまった方が多い問題でしょう。
割引債の課税は、「発行時に」原則として18%の所得税が徴収されて課税関係は終了するのです。したがって、「支払う際に」としている選択肢2が誤りの記述になります。他の選択肢の記述はともかくとして、この知識は、おさえておかなければいけない知識です。解説を聞いて、それなら、知ってたよ・・・とがっかりされている方も多いかもしれませんが、間違えてしまったものは仕方ありません。試験本番では、こういうのにひっかからないように慎重に問題文を読んでいくようにしましょうね。

解答 3
各種控除に関する・・・・ではなくて、確定申告なしで適用できる所得控除・税額控除はどれか?と言う問題です。なんだか、今回のFP試験は、問題の落差が激しいですね。これは、基本中の基本。配偶者特別控除は、確定申告しなくても適用できますから、正解肢は3番ですね。これから、FP試験を受験される方は、特に、医療費控除・住宅ローン控除の初年度分については、適用を受ける場合、確定申告が必要となる点は必ずおさえておいてください。ここは、非常によく質問されるFP試験のポイントですよ!
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第18回 所得税の申告と納税

解答 2
個人住民税に関する問題です。個人住民税に関しては、FP試験対策的には、この問題に正解できる程度の概要をおさえておけば十分です。以下に、特に重要と思われるポイントを記しておきましたから、これからFP試験を受験される方は、参考にしてみてくださいね。正解肢(誤りの記述)については、住民税の基礎控除額、配偶者控除額(一般)は、ともに、33万円となっていますから、所得税より小さいが正しい記述となります。試験対策としては、どちらかというと、他の選択肢のほうが、重要ですから、これから、受験される方は、その他の選択肢をよく読んでおくようにしてくださいね。
● 参考 住民税の学習ポイント
・納税義務者は、その年の1月1日において都道府県内・市町村内に住所がある人である点
・前年の所得に対して当年度に税額を支払うことになっている点
・税率は、一律10%(道府県民税4%、市町村税6%)である点
・賦課納税方式である点(税務署長により税額が決定される)

解答 4
減価償却費に関する特例についての問題です。減価償却費は、原則としては、全期間にわたり必要経費として算入していくものとされていますが、3つほど、例外があるのです。この問題は、この3つの例外をすべて覚えてる?と質問しているようなものですから、この例外の要点を書き出してみましょう。
ア) 耐用年数が1年未満のもの、または、金額が10万円未満のものについては、購入金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とすることができる。
イ) 一定要件を満たしたものについて、10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年間で均等償却することができる。
ウ) 一定の中小企業者で青色申告書を提出する等一定の要件を満たした者について、30万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる(事業年度において年間取得合計額300万円を限度)。
これと問題文を見比べてみると、選択肢1=ウの記述、選択肢2=イの記述、選択肢3=アの記述 と対応していることがわかりますね。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番ということになります。FP試験対策的には、基本問題とまではいえないものの、このあたりは、できればおさえておいていただきたい学習ポイント。覚える努力ぐらいはしてみてくださいね。

解答 4
消費税に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4については、FP試験対策としては、「みなし仕入れ率は、業種によって異なる」ということだけ、おさえておけばOKですが、選択肢1、2は、絶対に、選択肢3もできればおさえておいていただきたい記述です。消費税は、学習項目が法人税と比べると少ない割には、出題頻度は、高めです。学習にはそれほど時間はかからないはずですから、法人税はお手上げという方は、消費税の学習に力をいれておきましょう。
● 参考
選択肢2の文中に「課税事業者を選択している・・・」とありますが、もちろん、これは、自ら進んで、税金を納める人になるという届出をだすという意味です。この点について、疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは、免税事業者(税金を納めなくても良い人)のままだと、消費税の還付(払いすぎた税金を返してもらうこと)をうけられないからと理解しておいてください。つまり、還付を受けるために、自ら進んで課税事業者となることがあるということですよ。

解答 1
会社と役員間の取引における法人税・所得税に関する問題です。正解を当てるだけなら、「役員へ寄付ってなんだよ!」の一言で正解出来てしまう問題ですが、まじめに説明すると、これは、経済的利益の供与にかかる税務に関する問題ですね。
経済的利益の供与とは、法人が役員等に対して金銭以外の物や権利を供与した場合も原則として給与として扱われるというものです。選択肢2、3の記述がこの典型例ですね。選択肢4については、「会社が役員から借り入れ」という部分に注意してくださいね。この場合は、無利息であっても、原則として税務上問題はありませんが、「役員が会社から借り入れ」である場合で、不当に低い利息、あるいは、無利息である場合は、やはり、経済的利益の供与として扱われることになります。利息は大丈夫なんて、間違った覚え方はしないように注意しましょう。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
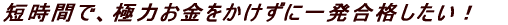
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2013年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 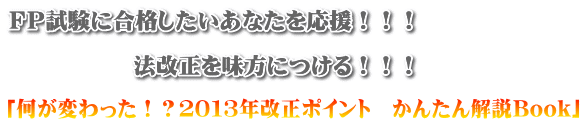
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 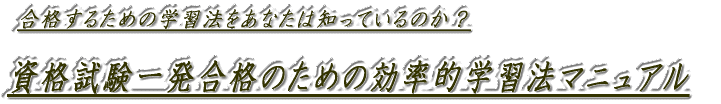
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 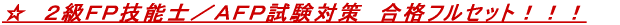 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2014年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|