2級FP技能士/実技試験(2008年5月個人資産相談業務) 第1問~第3問

解答
① 生計維持関係にある ② 18歳 ③ 5
公的年金の遺族給付に関する問題ですが、問題とはなっていない点によく問題として取り上げられる項目が含まれています。これから、学習される方は、こうした点にも注意してくださいね。
・社会保険では、「生計維持関係」がポイントになります。所得税でよくでてくる「生計を一」では、ありません。
・妻とありますが、社会保険では、「事実婚」も認められます。「民法上の配偶者」では、ありません。
・子に対する給付は、原則として、18歳到達「年度」の末日ですよ。
過去問を使って学習を進める際は問題には、なっていない点にも気を配るようにしましょうね。

解答
① ○ ② × ③ ○
①については、ややこしく書いてありますが、妻と子のそれぞれに支給されるわけではないと当たり前のことが書いてあるだけです。意味を読み取りましょう。
②の中高齢寡婦加算の支給は、妻の年齢が65歳になるまでとなっています。65歳といえば、老齢基礎年金の支給開始年齢ですね。中高齢寡婦加算は、妻自身が、自分の老齢基礎年金を受給できるようになると、支給停止となるのです。そして、この際に、支給される金額が減額とならないよう、差額については、経過的寡婦加算が支給されます。この説明を図にすると以下のようになります。
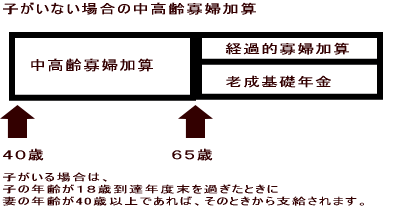
③は、供給調整に関する記述ですね。記述の仕方が、いかにも試験らしく難しく書いてありますが、この問題のような場合、平成19年4月1日以降は、老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせでの支給が基本となります。つまり、遺族厚生年金は、停止が基本。ただし、「遺族厚生年金をもらっていたほうが、多くもらえた・・・」というような場合には、「差額」が、遺族厚生年金として支給されます。

解答
2000000円×22.0232=44046400円
これは、正解しないといけない問題です。係数表の使い方については、「2級FP技能士 無料ポイント講座 第3回 係数表の使い方 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数」に掲載されていますから、よく読んでおいて下さい。問題は、○年間にわたって毎年○円ずつ受け取るには、今いくらいる?と聞いているのですよ。

解答
① オーバーパー ② 10 ③ 信用
① 満期時に償還差損が発生するのは、額面100円、発行価額101円というような場合ですね。これは、オーバーパー発行といいます。
② 個人向国債の変動金利といえば、10年ものですね。5年物は固定金利ですよ。これは必ずおさえておきましょう。
③ 格付けとは、AAAやAaaといったものですね。信用リスクとは、発行元がつぶれてしまったり、約束を守れなかったりするリスクのことをいいます。

解答
所有期間利回り
① (102.5-100.5)/5=0.4
② (0.4+2.1)=2.5
③ 2.5/100.5×100=2.4875・・・・・2.49%
債券の利回り計算については、「2級FP技能士無料ポイント講座 第13回 債券の利回り計算の考え方」にてご確認ください。「公式丸暗記チャレンジ」なんて、やめてくださいね。時間の無駄です。電卓で計算する場合は、上記手順で計算するとスムーズに計算できますよ。

解答
① × ② ○ ③ ○
金利と債券の関係に関する問題ですね。一見ややこしそうですが、2級FP技能士/AFP試験の範囲であれば、簡単です。
①については、金利が1%から3%へ上昇した場合、1%の債券がほしいか3%の債券がほしいか考えてみてください。3%の方がほしいでしょう?では、1%で金利上昇前に発行された債券の価格は、下落すると考えて良いですね。
②については、極端に考えましょう。償還が明日である場合、金利がどうあれ、明日になれば、額面金額が返ってくるのですから、あまり気にならないような気がしませんか?
③については、何をいってるのだか・・・。問題のための問題です。クーポンレートとは、利率のことです。固定金利なのですから、変わりませんよ。

解答
① 給与所得の金額(給与所得後の金額)
12000000円×5%+1700000円=2300000円
12000000円-2300000円=9700000円
② 源泉徴収税額
9700000-2500000円=7200000円
7200000円×23%-636000円=1020000円
FP 実技試験 恒例の所得税の計算問題です。しかも、この問題の難易度は、低めです。2問とも絶対に正解してくださいね。
① 給与所得の計算は、Aさんの給与収入金額に対応する給与所得控除をみつけて、所得金額を計算すれば出来上がりです。
②については、所得控除をひけたかどうかがポイントになりますね。所得にそのまま税金がかかるのではありません。所得税の計算の流れは、「2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~ 第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)」を参照して頭に入れておいてくださいね。

解答
① 35 ② 個人年金保険料 ③ 12月31日
寡婦控除とは、珍しいですね。①については、知らなくても特に気にする必要はありません。知っているに、こしたことはありませんが、あまり出題されませんから、他の基本的な控除をしっかり覚えることを優先させてくださいね。
生命保険料控除では、生命保険料と個人年金保険料について、それぞれ最高5万円まで控除をうけることができます。
年齢の判定は、年末時点でおこないます。所得税は、個人が1月1日~12月31日の間に得た所得に対して課税されますから、12月31日が区切りになるのは、納得できますよね。

解答
① ○ ② × ③ ×
この問題もぜひ、正解したい問題ですが、特に②だけは、絶対に間違えてはいけません。サラリーマンであっても確定申告が必要になるパターンは、FP試験の常連中の常連。学科・実技どちらでも頻繁に出題されます。他の確定申告が必要になるパターンについても、必ずチェックしておきましょう。
① 住民税の税率は、H19年度分より、一律10%(道府県民税4%、市町村税6%)となりました。
② 医療費控除や住宅ローン控除の初年度分等の年末調整で精算できないものに関してはサラリーマン等であっても確定申告が必要となります。
③青色申告のできる人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。給与所得者は、青色申告をすることはできません。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
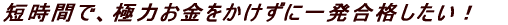
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 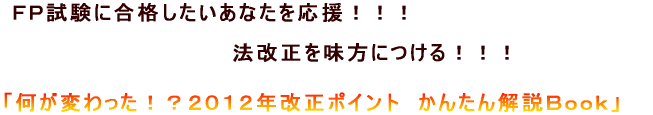
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 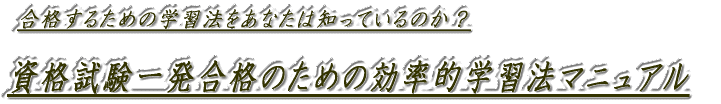
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 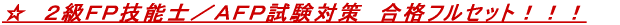 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年-2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()

![]()
