2級FP技能士/実技試験(2009年6月個人資産相談業務) 第1問~第3問

解答 ① × ② ○ ③ ×
公的年金および公的医療保険に関する問題です。なかなかレベルの高い問題ですね。ギリギリ学習しきれるかどうかの瀬戸際にあるような知識を問う選択肢が並んでいますから、2問正解できれば、合格ライン。この中では、②の記述が最もよく出題されますから、これだけは最低限おさえておくようにしましょう。
解説
① 誤りの記述です。60歳以後の厚生年金加入期間分は、老齢基礎年金には反映されません。老齢基礎年金の加入期間が20歳から60歳とされているためで、20歳以前、60歳後の厚生年金加入分は、経過的加算として年金額に反映されることになります。経過的加算については、2級FP技能士無料ポイント講座内にある基本モデル、解説ページで確認しておいてくださいね。
② 正しい記述です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。記述にあるように、この場合は、保険料は全額自己負担となります。
③ 誤りの記述です。被扶養者の認定基準として130万円は有名ですが、これは、60歳以下の方の場合。いわゆるひっかけ問題ですね。年齢が60歳以上である場合は、年間収入が180万円未満でかつ扶養者の年収の50%未満であれば家族の被扶養者として健康保険に加入することができます。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 ~パーソナルプランニング~
第5回 老齢年金制度の基本
第14回 経過的加算とは? 65歳からの老齢厚生年金

解答 ① 子のある妻または子 ② 4分の3 ③ 中高齢寡婦加算
遺族年金に関する問題です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件は、必ず違いを比較して覚えておきましょう。遺族基礎年金は、子がキーワード。子がいない妻や夫は、遺族基礎年金を受け取ることができないのです。したがって、①には、「子のある妻または子」がはいります。
また、支給される年金額については、遺族基礎年金の基本年金額は、792100円、遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 となります。これもやはり、あわせておさえておきたいところです。
最後の中高齢寡婦加算については、①の遺族基礎年金の支給要件とあわせて考えましょう。遺族基礎年金は、子供のある妻を対象者としていますから、子供が、18歳到達年度末に達するなど要件を満たさなくなると支給されなくなりますね。しかし、これでは、残された妻が生活していくのが、大変になってしまいますから、一定要件を満たす妻には、遺族厚生年金から中高齢寡婦加算が支給されるのです。中高齢寡婦加算の支給要件についても、時折出題されますから、これから、FP試験を受験される方は、できれば以下の支給要件もおさえておいてくださいね。年齢だけでもチェックしておくと・・・・・
○ 中高齢寡婦加算の支給要件
・夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で、子供がいないこと。
・夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること。
・遺族厚生年金が、長期要件により支給される場合は、死亡した夫の厚生年金被保険者期間が原則として20年以上(中高齢の特例適用可)あること。

解答 ① 1260200 ② 792100 ③ 1676 ④ 1656500
老齢年金の見込み金額の計算に関する問題です。こりゃ、難しいですね・・・・。ただ、①の報酬比例部分の計算は、資料より、対応する数字を見つけて、計算するだけ、②については、老齢基礎年金の満額の金額を記入するだけですから、ここまでは、計算式の意味をしっかり理解した上で、正解できるようにしておきましょう。
③については、定額部分の金額を覚えておかないと答えようがありません。一応、2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載はされていますが、ま、覚えていた人は、少ないでしょうねぇ・・・。
④については、さらに難易度が上がって、経過的加算の計算まで要求されています。問題1 ①で解説したとおり、老齢厚生年金と老齢基礎年金では支給金額に差額がでることがありますから、これが経過的加算として、支給されることになるのです。2級FP技能士試験でここまでの計算を要求するのは、ちょっと鬼すぎるような気が・・・・。ま、これは出来なくても仕方無しです。この問題が、全問正解できた方は、1級FP技能士、CFPを目指されると良いと思いますよ。
● 問題3 全計算過程
① (36万円×0.0075×372ヶ月+50万円×0.005769×82ヶ月)×1.031×0.985
=(1004400+236529)×1.031×0.985 = 1260206・・・・50円未満切捨て = 1260200円
② 792100円×454ヶ月/480ヶ月 = 749194・・・・(注 計算結果が②の解答ではありません)
③、④ 報酬比例部分の金額 + 経過的加算の金額(定額部分の金額-基礎年金額) + 加給年金額 の計算をおこないます。
1260200円 + (1676円×(372ヶ月+82ヶ月)×0.985 - 792100円×454ヶ月/480ヶ月) + 396000円
= 1260200円 + 300円 + 396000円 = 1656500円
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 ~パーソナルプランニング~
第6回 老齢基礎年金の受給金額
第11回 特別支給の老齢厚生年金 定額部分の詳細
第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細
第14回 経過的加算とは? 65歳からの老齢厚生年金

解答 ① ○ ② × ③ ×
10年固定利付国債と個人向国債(変動金利型)に関する問題です。2つの国債を混ぜられると難しいように感じるかもしれませんが、個人向国債の知識だけあれば、正解できるような気が・・・。できれば、得点を稼いでおきたい問題です。
① 正しい記述です。一般的に、金利の下落していく局面では、固定金利商品での運用のほうが有利となります。また、10年固定利付債の中途換金は、市場で売却することになりますが、この場合、金利の下落していく局面では、一般的に、債券価格は上昇することになるため、売却差益を得ることができる可能性も高くなります。
② 誤りの記述です。10年固定利付債は、毎月発行されていますが、個人向国債の募集は、年4回(募集は3・6・9・12月。発行はその翌月)となります。
③ 誤りの記述です。国債を購入するとは、国にお金を貸してあげるということですよ。ですから、国が破綻しない限り、元本や利子は、保証されます。ただ、絶対に安全とはいえませんよ。国が破綻することもありえますからね・・・。

解答 ① 16000 ② 7000000 ③ 雑
10年利付債券を購入した場合の税制に関する問題です。②のマル優制度については、最近、あまり出題がなかったので、初耳と言う方もいらっしゃるかもしれませんが、①、③については、確実に正解したいところ。利子にかかる税率、償還差益の扱い、売却差益の扱い、それぞれ整理して覚えておくようにしましょう。
① 金利は、問題より2%となっていますから、税金を差し引くと、以下の計算より、税引き後の利子の金額は16000円となります。
100万円×2%×(1-0.2)=16000円
② マル優、特別マル優は、それぞれ元本350万円までが非課税となりますから、この合計の額面金額700万円までの利子については、非課税となります。
③ 債券の税制において、ここは、非常によく聞かれるポイントです。これから、FP試験を受験される方は、償還差益は雑所得、売却差益は、非課税、この両方を覚えておきましょう。

解答 ① 2.06% ② 2.01%
債券の利回り計算に関する問題です。これは、正解必須!間違えてしまった方は、よく2級FP技能士無料ポイント講座を読み返しておいて下さい。こういうところで、点数を落とすていると合格は厳しいですよ!
① 応募者利回り
投資金額 = 購入金額 = 99.5円
1年分の利息 = 100円×2% = 2円
1年分の償還差益 (100円-99.5円)/10年 = 0.05
(2+0.05)/99.5 ×100 = 2.060301・・・・・小数点以下第3位 四捨五入 = 2.06%
② 直接利回り
投資金額 = 購入金額 = 99.5円
1年分の利息 = 100円×2% = 2円
2/99.5×100 = 2.01005・・・・・・・・小数点以下第3位 四捨五入 = 2.01%
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~金融~
第13回 債券の利回り計算の考え方
第14回 その他の利回り計算

解答 ① ○ ② ○ ③ ○
源泉徴収票に関する問題とはなっていますが、本質は、所得税の基礎知識を問う問題ですね。これは、全問正解と生きたいところです。
① 正しい記述です。給与所得は、給与収入-給与所得控除 の算式により計算されます。
給与所得控除の金額 = 1200万円×5%+170万円 = 230万円
給与所得 = 1200万円-230万円 = 970万円
② 正しい記述です。配偶者控除の対象となる配偶者は、年間合計所得金額が38万円以下であること が要件のひとつとなります。この金額は必ずおさえておくようにしましょう。
③ 正しい記述です。資料内に、給与賞与以外の収入はないとされていますから、この記述は正しい記述と言えます。試験対策としては、給与の年間収入が2000万円を超えていなくても、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている人など、一定の場合は、確定申告が必要となる点にも注意しておきましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第4回 給与所得とは?
第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
第18回 所得税の申告と納税

解答 ① 380000 ② 1010000 ③ 1351000 ④ 基礎
所得税の所得控除に関する問題です。2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでいた方は、正解できる問題ですね。同じような例題が掲載されていますよ。配偶者控除や扶養控除の控除額は、非常によく質問されますからね。この辺は、ど忘れすら発生しないぐらい、しっかり頭に叩き込んでおいてくださいね。
① 配偶者控除の金額 = 38万円
② 扶養控除の金額 = 特定扶養1人+一般扶養1人= 63万円 + 38万円 = 101万円
③ 社会保険料控除 = 源泉徴収票より1351000円
④ 基礎控除は、すべての納税者に適用される所得控除です。所得控除の金額を計算する上でないということはありません。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)

解答 ① 一時 ② 500 ③ 贈与
一時金として受け取る満期保険金に関する税務についての問題です。これは、かなりのサービス問題ですよ。保険の契約形態ごとの課税の違いや一時所得の計算などは、FP試験では最頻出の学習項目。このあたりでは、わからないことがないように学習を進めておきましょう。
契約者 = 満期保険金受取人となっている保険契約において、一時金として受け取る満期保険金は、原則的には、所得区分は、一時所得となります。一時所得の金額は、
総収入-収入を得るための支出金額-特別控除50万円
の算式によって計算され、この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されます。一時所得の金額とは、1/2を乗じる前の金額のことを言う点には、注意しましょう。
最後の③の問いについては、そもそも相続が発生していませんから、相続税のはずはなし!お金が、夫 → 保険 → 妻 へと流れるということですから、これは、どう見ても贈与税の課税対象ですね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第8回 一時所得とは?退職所得とは?
2級FP技能士無料ポイント講座 ~リスク管理~
第8回 受け取り保険金と税金
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
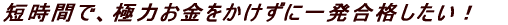
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 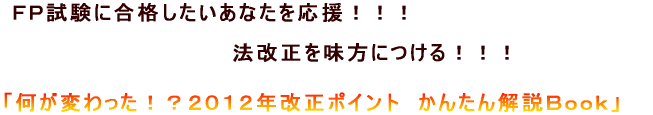
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 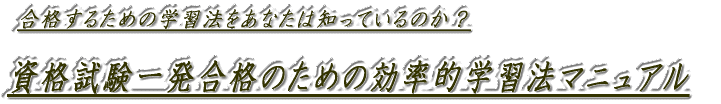
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 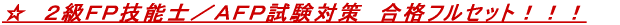 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年-2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
![]()
