|

解答 ア) 3 イ) 5 ウ) 9
外貨預金と外貨MMFに対する課税についての問題です。これは、よく聞かれる質問ですね。利息・分配金については、20%の源泉分離課税と同じ扱いになりますが、為替差益については、扱いが異なり、外貨預金の場合は、雑所得、外貨MMFの場合は、非課税扱いとなるのです。これは、覚えておきましょうね。
あっ、そうそう、本当は、外貨預金の為替差益は、雑所得と言い切ることはできません。為替予約をおこなった場合は、為替差益も含めて源泉分離課税扱いとなりますから、問題に「原則として」と付け加えておきましょう。

解答 4
健康保険の傷病手当金に関する問題です。う〜ん。なんだこれ?答えが、選択肢の中に書いてありますよ。選択肢1では、「休んだ日について支給される」とあり、選択肢4では、「入院している場合にのみ支給される」とありますから、この2つの記述は、どちらかが誤りであることがわかりますね。つまり、この問題は、実質、2択問題です。選択肢1と選択肢2の記述については、できればおさえておいていただきたい記述ですから、この2つの選択肢は、よく読んでおくようにしましょう。

解答 ア) 2 イ) 4
遺族年金に関する問題です。まず、遺族基礎年金は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻に対して支給され、遺族厚生年金は、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母に支給される点を必ずおさえておきましょう。この問題の場合は、子のある妻が対象者となっていますから、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されることになりますよ。
さて、アの正解である遺族基礎年金ですが、これから、FP試験を受験される方は、図を良く見ておきましょう。段になっているでしょう?これは何でしょうか?
遺族基礎年金の支給は、原則として、「生計維持関係にある子供が18歳に到達する年度末まで」となっていますから、途中で、長男が、支給対象から、はずれるということをあらわしているのですよ。
さらに、長女が18歳に到達する年度末となると、遺族基礎年金の支給はなくなります。しかし、子供が大人になったからとはいっても、妻が一人で生活していくのは、大変ですよね?
ですから、一定要件を満たす妻には、遺族厚生年金から中高齢寡婦加算が支給されることになります。
中高齢寡婦加算の支給要件には、「夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること。」という要件があり、この問題の妻の場合は、これに該当しますから、イは、中高齢寡婦加算があてはまるのです。

解答 13536万円
バランスシートに関する問題です。AFP試験を受験される方は、資産 = 負債+純資産の関係は、頭にいれておかないと駄目ですよ。この手の問題は、AFP試験では、よく出題されます。ちょっと、ひねりがはいって、一部、自分で計算しないといけない箇所がありますが、それほど、難しい問題ではありませんから、確実に得点できるよう、慎重に計算していきましょう。
● 計算過程
外貨預金12万ドルを1ドル=98円で、円に直すと、12万ドル×98円 = 1176万円
預金等の総額 = 1176万円+1800万円+2800万円 = 5776万円
生命保険の解約返戻金相当額 300万円+960万円 = 1260万円
資産合計額 = 5776万円 + 800万円 + 1260万円 + 3400万円 + 5700万円 + 200万円 + 100万円 =17236万円
負債合計額 = 1100万円 + 2600万円 = 3700万円
純資産の金額 = 17236万円 − 3700万円 = 13536万円

解答 2
配偶者特別控除および扶養控除に関する問題です。奥さんのパート収入は、108万円ということですから、給与所得控除をひくと43万円となります。配偶者控除は、年間合計所得金額が38万円以下でないとうけられませんから、配偶者控除は受けられず、これだけなら、配偶者特別控除の対象者となります。
しかし!!!
ひっかけですねぇ〜。配偶者特別控除の対象者とするためには、納税者の合計所得金額が1000万円以下であることが要件となるのです。納税者、つまり、夫の合計所得金額を確認すると1135万円とありますから、配偶者特別控除の対象とすることはできません。したがって、アには、0がはいるのです。
扶養控除は、生計を一にしている合計所得金額38万円以下の配偶者以外の扶養親族がいる場合に受けることができます。長男の所得金額は、200万円とありますから、この場合は、二男だけが対象者となりますね。ここで、重要なのは、年齢のチェック。二男の年齢は、現在、21歳、年末時点年齢、22歳となりますから、特定扶養親族に該当しますね。したがって、扶養控除の控除額は、63万円となるのです。
以上の話をまとめると、正解肢は、選択肢2番ですね。ちょっと、難しかったかもしれませんが、問題としては、良い問題です。配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は、特によく出題される学習項目ですから、間違えてしまった方は、もう一度、見直しておきましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
第12回 扶養控除とは?

解答 ア) 1 イ) 8 ウ) 6
外貨預金の利回りに関する問題です。普通に外貨預金の利回りを計算していけば、正解できる問題ですが、AFPの問題としては、少し難しいですね。順をおって解説していきましょう。
● 計算過程
・投資金額の算出
5万ドル×98円 = 490万円 となります。
ポイント TTSとTTBは、絶対に間違えないようにしましょう。Sは、SELL、円を売る = 外貨にかえるとき と覚えておけばOKですよ。
・税引き後の利息金額の算出
5万ドル×2%×6/12 ×(1−0.2) = 400ドル となります。
ポイント 利息は1年分で表示してありますから、預入期間に応じたものに直さないと駄目ですよ。それが、×6/12の部分です。×(1−0.2)は、税金の計算です。問題によっては、税金は一切考慮しないとあったりすることもありますから、計算条件をよく読むようにしましょう。
・元利合計額50400ドルを円に戻す計算
50400×94.5 = 4762800円
ポイント ここも、TTSとTTBの間違いに注意です。BはBUY 円を買う = 円にかえるとき、と覚えておけばOKですよ。
・利回りの計算
儲け金額 = 4762800円−4900000円 = ▲137200円
利回りとは、1年間の収益の合計を投資金額でわったものをいいますから、この半年分の損失を1年換算すると、
▲137200円×12/6=▲274400円 となり、利回りを求めると
利回り = ▲274400円/4900000×100 =▲5.6% となります。
以上より、正解番号を選ぶと、アは、1番、イは、8番、ウは、6番となります。しかし、この問題、正解できるだけでなく、早く解くことも大事ですよ。もしも、試験本番で、この問題のように、時間のかかりそうな計算問題が出題されたら・・・ひとまず、とばしてしまってもよいですよ。これに、かかりきりになり、残りの問題をやる時間がなくなった・・・なんてことがないように注意しましょうね。

解答 1
土地等の譲渡所得に関する問題です。取得費加算の特例等は、考慮しないとありますから、普通に、分離課税の譲渡所得について、考えればよいです。分離課税の譲渡所得では、特別控除を差し引いたり、1/2を乗じたりしませんよ。これは、総合課税の長期譲渡所得のお話です。分離課税の長期譲渡所得となるのは、相続人が、被相続人(三郎さん)の取得日を引き継ぐからですよ。
参考 平成21年・22年中に取得した土地等の特別控除
平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に個人・法人が取得した土地等については、譲渡の年の1月1日において5年超の所有期間となっていることを条件に1000万円の特別控除(法人の場合は1000万円の損金算入)が認められることになりました。

解答 2
老齢基礎年金を繰り上げて受け取った場合の受け取り金額を求める問題です。とりあえず、445/480は、よいですね。納付月数に応じた金額が支給されると言う意味ですよ。ここまでが、65歳から受け取ることのできる老齢基礎年金額の計算です。
繰り上げ請求をした場合の減額率は、覚えていますか?
1ヶ月ごとに0.5%減額でしたね。
この問題の場合は、60歳から繰り上げ請求するといっているのですから、65歳までの5年分 = 60か月分を減額しないといけません。これを算式に直し、計算すると
1−0.5%×60 = 70%
となりますから、正解肢は、選択肢2番となるのです。老齢基礎年金の受け取り金額の計算や繰上げ請求をした場合の減額率は、FP試験では、非常によく出題されます。間違えてしまった方は、よく見直しておいてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給

解答 ア) 市町村 イ) 75 ウ) 1
後期高齢者医療制度に関する問題です。後期高齢者医療制度では、75歳以上になると、現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられることになります。運営(保険者)は、問題にあるとおり、都道府県(後期高齢者医療広域連合)ですが、保険料の徴収の窓口は、市区町村となります。自己負担割合については、原則は1割負担ですが、現役並み所得を有する者の負担額は3割となっています。
FP試験ポイントとしては、対象者となる年齢や自己負担割合には、特に注意しておきましょう。後期高齢者医療制度は、創設以来、すっかりFP試験の常連問題となっています。これから、FP試験を受験される方は、概要ぐらいはおさえておいてくださいね。

解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ×
国民年金基金に関する問題です。国民年金基金は、自営業者などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ制度です。問題にはなっていませんが、国民年金基金の掛け金には上限があり、原則として月額68000円が限度であり、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、あわせて68000円が限度となる点もあわせて覚えておいてください。この点もよく質問されますよ。
● 解説
ア) 正しい記述です。受け取る年金については、もちろん公的年金等控除の対象となります。
イ) 正しい記述です。脱退については、問題にあるとおり、 一旦加入すると、一定の事由に該当する場合を除き、任意に脱退することはできません。
ウ) 誤りの記述です。第三号被保険者は、加入できません。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第18回 国民年金基金の概要
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
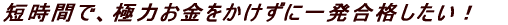
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 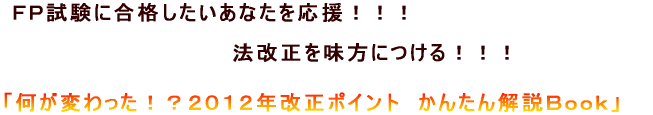
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 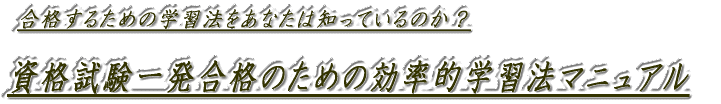
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 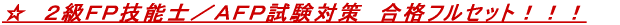 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
