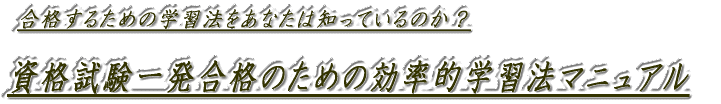|
パーソナルプラン

解答 3
ファイナンシャルプランナーの業務と関連法規に関する問題です。この手の問題は、まず、いの一番に、「資格がないと具体的なことは×」という大原則を思い出すようにしましょう。この大原則にそって問題をよくみてみると・・・・・・選択肢1には、「概要について」という言葉が、選択肢2、4には、「一般的な」という言葉が発見できますね。よって、資格がないのに、もっとも具体的な行為をおこなっているのは、選択肢3番。これがそのまま正解肢となります。このパターンの出題は、ファイナンシャルプランナーの資格試験において、よくある出題パターンです。ここは、さくっと得点を頂いて、さっさと次の問題へいきましょう。

解答 4
フラット35の利用者調査報告書の読みとり問題です。フラット35は、平成21年に利用条件等が一部変更されており、フラット35に関する出題があるだろうとは思っていましたが・・・・こうきましたか・・・・・。ま、選択肢1、2については、資料をみてのとおりですし、実質的には、選択肢3、4の2択問題。むしろ、改正点を出題されるより正解しやすかったかもしれませんね。選択肢3、4について計算してみると、
選択肢3は、
建売住宅 = 35509/104 = 341.4326・・・(千円)
新築マンション = 35937/75.3 = 477.25099(千円)
ですから、正しい記述、選択肢4は、
建売住宅 = 6238/35509 × 100 = 17.567・・・%
新築マンション = 7336/35937 × 100 = 20.413・・・%
ですから、誤りの記述であることがわかります。よって、正解肢は4番となります。意表をつかれたような形での出題ですから、、えっ・・・?と思われた方も多かったかもしれませんが、冷静さを取り戻せれば、正解できる問題だと思いますよ。

解答 3
キャッシュフロー表に関する問題です。AFP実技試験ではよく出題される問題ですが、学科試験での出題は、久し振りのような・・・。ま、さすがに、正解肢3番の記述内容は、どんなテキストにも記載があると思いますから、正解できた方は多い問題ではないでしょうか?AFP試験を受験される方は、このあたりは必須知識ですが、FP技能士試験を受験される方も、概要程度はおさえておくようにしましょうね。
選択肢1 誤りの記述です。可処分所得とは、簡単にいえば、自由に使えるお金のことをいい、収入−(所得税+住民税+社会保険料)で計算されます。要は、収入から、国が強制的に持っていく分をひいた金額ということですね。収入と支出の差額のことではありませんよ。
選択肢2 誤りの記述です。キャッシュフロー表は、ライフイベントにそった将来の家計の収支予測表ですから、当然、収入を伴うライフイベントも考慮されます。そもそも、収入を無視した家計の収支予測では、意味がありませんよねぇ・・・。
選択肢3 正しい記述です。
選択肢4 誤りの記述です。時価ですよ。時価!個人バランスシートは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものですよ。買ったときのままの価格を記載していたら、現状の家計の資産内容が把握できません・・・・・。

解答 4
公的医療保険に関する問題です。突然、難易度の高めの問題がやってきましたね・・・・。選択肢2、3(誤りのきじゅつ)は、2級FP技能士試験としては、ややレベルが高めですから、これから、FP試験を受験される方は、選択1および4の解説をよく読んでおくようにしましょう。
選択肢1 誤りの記述です。協会けんぽの健康保険の保険料(旧 政府管掌健康保険)については、平成21年9月より、都道府県毎の保険料率に移行されています。全国一律ではありません。
選択肢2 誤りの記述です。これは、細かい点に関する記述ですね。任意継続被保険者制度を利用した場合の健康保険料は、基本は、退職時の標準報酬月額をもとにして算出されます。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円とされます。
選択肢3 誤りの記述です。健康保険の被扶養者となる場合、被保険者の収入によって生活している直系尊属、配偶者、子供、孫、弟妹であれば、同居の有無は条件とはなりません。
選択肢4 正しい記述です。後期高齢者医療制度では、75歳以上になると、現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられることになります。

解答 1
雇用保険の基本手当てに関する問題です。平成21年中に、非正規雇用者への給付に関する改正が多くおこなわれたにもかかわらず、直球・ど真ん中の問題ですか・・・。試験問題を予想するのは、難しいものですねぇ・・・。
ア) 一般離職者(定年や自己都合退職の場合)の場合の基本手当ての給付日数の上限は、150日です。ちなみに、下限は、90日ですよ。
イ) 待期期間は、7日間です。もしも、離職した理由が、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加え、最長3ヶ月間の給付制限があります。
ウ) 基本手当ての受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この期間経過後は、給付日数が残っていても給付は受けられません。

解答 3
老齢年金の給付に関する問題です。おっと、出ましたねぇ!!!2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでいれば、秒殺出来る問題ですよ。老齢年金の基本モデル、そのまんまですから、解説は、なしでOKですよね?
おもむろに、昭和25年生まれの夫とか、書いてありますが、言い換えると、平成22年に60歳となる男性のこと。このように、今年60歳となる男性の年金支給がどうなっているのか?という点は、FP試験において、非常によく出題されますから、必ずチェックしておくようにしてくださいね。
☆ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第5回 老齢年金制度の基本

解答 2
遺族年金に関する問題です。正解肢をバシっと射抜くのは、難しかったかもしれませんが、まず、ア)の記述は、必ず正解しましょう。遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻ですから、配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合は、必ず子の加算があるのです。ここさえわかっていれば、選択肢2、4の2択問題となり、ウ)が実はものすごく簡単な質問であることに、気付ければ、とっても簡単に正解肢を選ぶことができます。
どこが簡単か?ですか?
だって、妻は、国民年金にしか加入していないのですから、老齢厚生年金など、もらえるはずがありませんよ。老齢年金は、自分が加入していた年金保険から支給されるものですからね。したがって、正解肢は、2番なのです。
一見、難しそうにみせておいて、実は簡単というのは、FP試験の王道的な出題パターンです。難しそうにみえても簡単にあきらめるのは、やめておきましょう。
※参考 中高齢寡婦加算
遺族基礎年金は、子供のいる妻を対象者としていますから、子供が、18歳到達年度末に達するなど要件を満たさなくなると支給されなくなります。しかし、子供がいなくなったとはいっても、妻が一人で生活していくのは、大変ですから、一定要件を満たす妻には、遺族厚生年金から中高齢寡婦加算が支給されるのです。
※ 参考 経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金受給権者の妻が65歳に達したときに支給されます。妻の年金が老齢基礎年金に切り替わることにより、受け取り年金額が中高齢寡婦加算の額を下回らないようにするための措置です。

解答 4
確定給付型の企業年金に関する問題です。これは、難しいというより、ここまで手がまわらなくても仕方のない問題ですね。駄目なら駄目で仕方ありませんから、割り切って次へいきましょう。
選択肢1 正しい記述です。いわゆる3階部分の年金のうち、適格退職年金については、記述にあるとおり、廃止となることが決まっています。
選択肢2 正しい記述です。移行先としては、中退共のほか、厚生年金基金・確定給付企業年金・企業型確定拠出年金があります。
選択肢3 正しい記述です。厚生年金基金は、厚生年金の一部を代行し、一定の上乗せ給付を行う年金です。とは言っても、このご時勢、運用がそう簡単にいくはずもなく、足りない分を企業が補填するハメに・・・・。これを避けるために、おこなわれたのが、一昔前によく聞いた代行返上というやつなのです。
選択肢4 誤りの記述です。厚生年金基金の掛け金については、原則的には、事業主と加入者が折半で負担します。ただし、厚生年金基金の加算部分については、規約に定めることにより、事業主の負担を増やすことも可能です。

解答 3
住宅ローンの借り換えに関する問題です。正解肢を選ぶことができた方が多そうな問題ですね。借り換えをおこなう場合は、単純に、金利を見比べるだけではなく、諸費用をしはらってもなお効果があることを必ず確認する必要があります。ま、新たに抵当権を設定しないと言っている(=無担保で貸すということになります)時点で、おかしな話ですから、正解肢は選べてしまいますけどね。
これから、FP試験を受験される方に、ぜひ覚えておいていただきたいのが、選択肢1番の記述。昔は、フラット35は借り換えに利用できなかったのですが、平成21年6月4日以降、借り換えの利用も可能となったのです。これは、覚えておくようにしましょう。

解答 2
公的教育ローンに関する問題です。正解を選ぶのは、難しいかも?な問題ですね。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、同じ教育資金でも、性質が違いますから、重複して利用することは可能です。教育一般貸付の借主は保護者、奨学金の借主は学生本人ですからね。しかし、この正解肢は、ちと細かすぎのような・・・。選択肢4の記述は、昔からよく出題される定番問題ですから、この記述ぐらいは覚えておきましょう。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
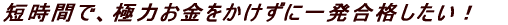
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2014年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 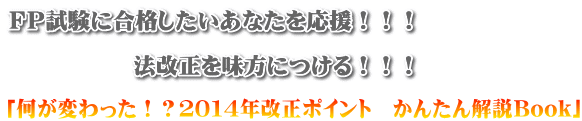
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 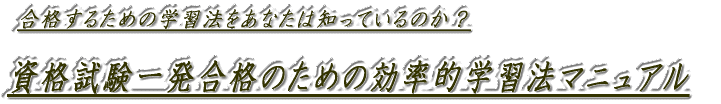
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 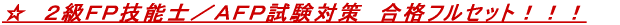 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2014年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|