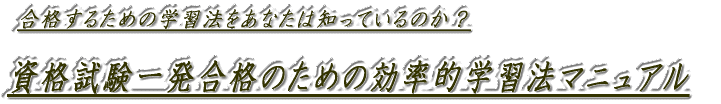2級FP技能士/実技試験(2010年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問

解答 ① ○ ② × ③ ×
公的介護保険に関する問題です。FP試験 社会保険の分野は、試験範囲が広く、なかなかここまで手がまわらないというのが本音だとは思いますが、それでも、②の記述の自己負担割合等ぐらいは、おさえておきたいところ。時間的な余裕がないような場合でも、できるだけ、概要ぐらいは目を通しておくようにしてくださいね。
① 正しい記述です。公的介護保険では、65歳以上の市町村内に住所を有する者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者を第2号被保険者とされています。第一号被保険者の場合は、要介護状態あるいは、介護状態となる恐れがある状態となった場合(要支援状態)に介護保険の給付(サービス)を受けることができますが、第2号被保険者の場合は、問題にあるような一定の老化に起因する疾病により、要介護状態になった場合に給付(サービス)を受けることができます。
② 誤りの記述です。介護保険では、原則として1割負担となっていますが、上限額が定められており、上限額を超えた分については、全額自己負担となります。
③ 誤りの記述です。ケアプランとは、介護サービスの利用計画書のことです。ケアプランの作成費用は全額介護保険より支払われます。

解答 ① 560 ② 140 ③ 市町村(特別区含む)
高額医療・高額介護合算制度に関する問題です。問題を聞いて、何これ???知らな〜いとあっさりあきらめてしまった方!いけませんよ。①、②に関しては、資料から数字を拾って、引き算するだけですからね!!!実技試験では、こういう問題も出題されることが多いですから、知らない内容の問題が出題されたとしても、とりあえず、考えてみるようにしましょう。
① 条件にて、Aさんは、一般に該当するとありますから、表中より、解答は560(千円)となります。
② 条件にて、Aさんが400(千円)、妻Bさんが300(千円)の自己負担があったとありますから、700(千円)−560(千円)より、解答は、140(千円)となります。なぜ、足すのか?なぜ、足したものから引くのか?については、文中に記載があります。
③ 介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区(23区のこと)となります。
☆ 参考 高額医療・高額介護合算制度
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、世帯内の医療費と介護費を合算して自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度のことをいいます。合算の対象となる期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までとなっています。

解答 ① 75 ② 180 ③ 社会保険料控除 ④ 均等割額
後期高齢者医療制度に関する問題です。う〜ん・・・・、学科試験でも出題がありましたが、後期高齢者医療制度は、廃止の方向で話が進んでいますから、こんなに取り上げられる必要もないように思うのですが・・・・。ま、どのみち、廃止されるにしても、一定の移行期間を経て新たな制度へとなるでしょうし、FP試験対策としては、概要を押さえておく感じで学習しておくと良いでしょう。
① 後期高齢者医療制度では、75歳以上になると、現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられることになります。
② 保険料の納付は、原則として、年額18万円以上の年金受給者については、年金より天引きとなっていましたが、文中にあるとおり、平成21年4月より、口座振替による納付も選択できるようになりました。
③ もちろん、後期高齢者医療制度の保険料も社会保険料控除の対象となります。これは、必ず正解してくださいね。
④ これは、難しい記述ですね。後期高齢者医療制度には、保険料の軽減措置がありますが、均等割額にも、所得割額にも、どちらにも軽減措置はあります。問題にある同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額に応じて・・・となっている軽減措置は、確かに、均等割額のほうの軽減措置ですが・・・・。ま、ここまでは、知らなくても当然です。気持ちを切り替えて、次へいきましょう。

解答 ① ○ ② × ③ ×
外貨預金に関する問題です。全問正解といきたい記述が揃っている問題ですね。ここまで、介護保険など、なかなか学習の手のまわりにくい分野からの出題でしたから、このあたりで挽回しておきたいところです。
① 正しい記述です。外貨預金の「利子」は、利子所得の対象となります。外貨預金の為替差益は、原則として「雑所得」ですよ。間違えないように覚えておいてくださいね。
② 誤りの記述です。まわりくどい記述の仕方になっていますが、こんなものに惑わされてはいけません。問題文の指示通りに適当な数値をあてはめて考えてみると、預入時100円 → 満期時99円ということですから、あきらかに損(為替差損)を被ることになります。
③ 誤りの記述です。外貨預金は、最初から、元本保証がない金融商品なのに、預金保険制度によって保護されるはずがありませんよ。

解答 5.83%
外貨預金の利回り計算に関する問題です。うわぁ・・・・無理!なんていっていてはいけません。所詮は、利回り計算。利付債券の利回り計算と、同じように考えていけばOK。確かに、ちょっと面倒くさいところはありますが、最終的にやることは、やっぱり、1年間の収益の合計/投資金額×100 の計算ですよ。どうみても、得点配分が高そうな問題ですし、ここは、ひとつがんばってみましょう。
● 計算過程
・計算前に確認すべき点
預入期間 = 1年
利回り = 1年間の収益の合計/投資金額×100
1年間の収益の合計 = 利息収入+為替差益(差損)
・投資金額の計算
1ドル=96円 → 1万ドル = 96万円
・利息収入(税引き後)の計算
1万ドル × 2% × (1−0.2) = 160ドル
満期時レート = 100円より、利息収入は、16000円
・為替差益の計算
満期時の円ベースの預金額 1万ドル×100円 = 100万円
為替差益 = 100万円−96万円 = 4万円
・利回りの計算
(1万6千円+4万円)/96万円 ×100 = 5.8333・・・・・・・・%

解答 ① レバレッジ ② ストップロス ③ スワップ
FX(外国為替証拠金取引)に関する問題です。うおっ・・・これはすごい。FP試験においては、FXは、脇役的に過去何度か出題があったものの、ここまで取引の内容について大きく取り上げられたのは、初めてではないでしょうか?ま、確かに、外貨投資といえば、今やFXですからね。今後は、出題が増えていくかもしれません。まず、FXとは、どのような金融商品であるのか?についてお話しておきましょう。
FXとは、一定の証拠金を証券会社等に預けることにより、この元手の何倍もの取引をおこなうことのできる金融商品です。投資対象は、世界各国の通貨で、売りからでも買いからでも、どちらからでも取引をおこなうことができます。今後のFP試験対策的には、円売りから入った場合は、円高に振れると利益となり、円買いから入った場合は、円安になると利益が得られる点もおさえておいてくださいね。
では、問題の解説をおこなっていきたいと思います。まず、①のレバレッジ効果ですが、この言葉は、FXだけの専門用語というわけではありませんよ!意味としては、元手の何倍もの取引ができる(少ない元手で、大きな収益を狙うことができる(大きな損失となることも当然あります))ということを指していますから、株の信用取引や不動産投資のお話の中でもでてきます。個別に覚えるのではなく、言葉の意味をおさえておくようにしましょう。
また、問題では、FXはハイリスク・ハイリターンの取引とありますが、これは正しい表現ではありません。一般にもこのように解説がなされていますから、今後もこの表現での出題となるのかもしれませんが、どのぐらいの倍率とするのか?は投資者自身が決定することができるわけですから、必ずしも、ハイリスク・ハイリターンの取引となるというわけではないのです。手持ち金額の範囲内で投資する(こうすると外貨預金や外貨MMFへの投資と為替リスクの大きさは同じぐらいになります)ことも可能なのですから、正しくは、投資者の選択によっては、極端にハイリスク・ハイリターンの取引となってしまう恐れのある取引となります。
さて、では問題に戻って②についてお話しますが、ストップロスは、日本語に直せば簡単。「損きり」ですよ。損きりとは、損失の拡大を防ぎ、一定範囲内の損失で留めるための措置ですね。ここで説明されているストップロスは、業者が、投資家保護のためにおこなう強制的におこなうロスカット取引ですね。もちろん、自分で業者の強制決済が入る前に、損きりすることも可能です。
③については、スワップポイントという名前はともかく、これでは、初めてFXについて学習する方には、文章の意味がわかりませんね。FXでは、金利の低い通貨を売って、金利の高い通貨を買うと両国の金利差が、利息(スワップポイント)となるのです。ただ、FXの場合は、利息がもらえることが確定しているわけではありません。先のお話とは逆に、金利の高い通貨を売って、金利の低い通貨を買うとスワップポイントを支払うことになります。

解答 ① × ② ○ ③ ×
所得税の譲渡所得に関する問題です。譲渡所得は、所得税の所得の中では、理解しづらい所得ですが、どうしても理解できないと思ったら、この問題で取り上げられているような箇所だけおさえておくとFP試験対策としては効果的です。試験対策という意味では、なかなか良い問題ですから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。
① 誤りの記述です。ゴルフの会員権の譲渡所得は、原則として、総合課税の譲渡所得となります。
② 正しい記述です。5年という数字はおさえておきましょう。
③ 誤りの記述です。生活に必要な動産の譲渡による収入は、原則として、非課税所得となります。非課税所得は、利益が出た場合には、課税がないかわりに、損失が出た場合に損益通算することはできません。
☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第7回 譲渡所得とは?

解答 ① 7800 ② 240 ③ 一時 ④ 8020
所得税の総所得金額を算出する問題です。これは、最低3つは正解しないといけませんよ。FP試験の実技試験では、所得税の総所得金額や税額を計算させる問題がよく出題されますが、この問題のレベルは、2級FP技能士 実技試験で出題されるものとしては、簡単な方です。総所得金額の計算や税額の計算については、問題集等を用いて、必ずよく練習しておくようにしましょう。
① 給与所得は、給与収入−給与所得控除の計算により求められますから、資料より計算をおこなうと7800(千円)となります。
② 譲渡所得には、50万円の特別控除がついているのがポイントですね。収入金額−取得費−譲渡費用−特別控除50万円の計算により、240(千円)となります。
③ 養老保険の満期保険金を受け取った場合は、収入金額−払込保険料総額−特別控除50万円 = 20万円が一時所得の金額となります。
④ この問題での唯一の難関ですね。長期譲渡所得および一時所得は、1/2前の金額となっていますから、他の所得と合算する際には、1/2を乗じた金額を合算しなければなりません。したがって、
780万円+12万円+10万円 = 802万円 → 8020(千円)が正解となります。
☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第7回 譲渡所得とは?

解答 ① 70 ② 380 ③ 10000
所得税の扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。①の老人扶養控除の年齢は、試験的には、ちょっと影が薄い部分ですが、②、③はFP試験では、非常によく質問される記述。もう少し深い部分まで、問われることもありますから、間違えてしまった方はしっかり復習しておきましょう。
① 扶養控除でいうところの老人とは70歳以上の方です。年齢の若い方の扶養控除は、こども手当ての支給の関係で廃止方向ですから、今後は、こっちのほうの出題が増えてくるかもしれませんね。
② 配偶者控除の適用要件は、必ずおさえておきましょう。年間合計所得金額が38万円以下というのは、最頻出の要件ですよ!
③ 配偶者特別控除の場合は、配偶者だけでなく、納税者自身にも適用要件があります。それが、これですね。納税者の合計所得金額が1000万円以下であることと言う要件は、非常によく出題されますから、必ずおさえておくようにしましょう。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
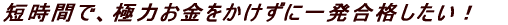
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2013年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 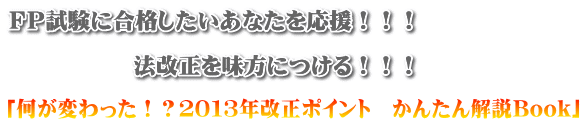
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 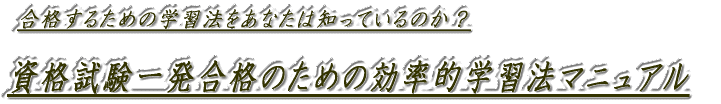
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 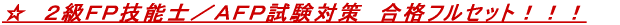 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2014年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
![]()