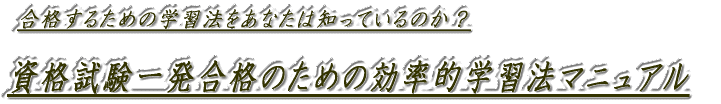2級FP技能士/実技試験(2009年5月個人資産相談業務) 第1問~第3問

解答 ① 2ヶ月 ② 20日 ③ なる
定年退職後の公的医療保険制度に関する問題です。任意継続被保険者と退職者医療制度についての質問ですが、退職医療制度については、もともとも出題率が高い項目ではない上に、廃止されることが決定されていますから、この問いについては、間違えても、あまり気にしなくても良いと思います。これから、FP試験を受験される方は、任意継続被保険者の解説についてはよく読んでおいてくださいね。
任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。ただし、保険料は、全額自己負担となります。また、傷病手当金、出産手当金が支給されないなど従前に加入していた健康保険とは異なる部分もあります。問題とされている部分以外では、これらの点についてよく質問されますから、覚えておいてくださいね。
③の退職者医療制度とは、市町村が運営する国民健康保険の中の制度です。問題にあるように、廃止されることになっています。なぜ、いまさら、出題されたのでしょう?はて・・・・?
退職者医療制度の被保険者になるのは、国民健康保険の加入者 であり、 65歳未満の者で、かつ、 厚生年金・共済年金の加入期間の合計が20年以上ある者で老齢年金の支給を受けている、または40歳以降の加入期間が10年以上ある者で老齢年金の支給を受けている者です。資料を確認すると、退職後、Aさんは、この条件にあてはまることになりますから、退職者医療制度の対象者となるのです。

解答 ① 360000円 ② 7.500 ③ 792100円 ④ 227900円
報酬比例部分および老齢基礎年金の受給金額に関する計算問題です。2級FP技能士試験にしては、なかなか、ハイレベルな問題ですね。報酬比例部分の計算では、平成15年3月以前と平成15年4月以降にわけて計算するということを知っていれば、①には、平成15年3月までの平均標準報酬月額である36万円が記入できると思うのですが、②の新乗率と旧乗率については、知らない方も多かったかもしれません。
これは、従前額補償といって、旧算出式で算出された年金額と新算出式で計算された年金額と見比べて旧算出式で算出された年金額の方が多い場合は、こちらの金額が年金額とされることになっているのです。当面は旧方式で算出された年金額が支給されることになっていますから、②は、旧乗率である7.500が正解となるのです。
③については、老齢基礎年金の満額の金額を記入すればOK。老齢基礎年金にフル加入している場合は、792100円×480/480と覚えておくと、こうした計算問題にも対応できて良いと思いますよ。計算しろといわれることも良くありますから、これから受験される方は、そのつもりでいてくださいね。
④については、配偶者の加給年金額を知らないと答えようがありませんね。平成20年、平成21年度価額ともに、227900円です。なかなか、ここまで覚えられませんよねぇ・・・・。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 ~パーソナルプランニング~
第6回 老齢基礎年金の受給金額
第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細
第13回 加給年金と振替加算

解答 ① ○ ② × ③ ○
老齢基礎年金の繰り上げ支給に関する問題です。すべての問いを知っていて正解できた方は、素晴らしいと思いますが、この問いのうち、特に、①と②については、非常に良く出題される箇所ですから、これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておきましょう。
繰上げ支給を希望すると、年金を早く受け取ることが出来るかわりに、支給を希望した年齢から65歳になるまでの月数に応じて、0.5%減額されることとなり、この減額された年金額が一生涯続くことになるのです。②にある0.7%とは、繰下げ支給を希望した場合の増額率ですね。
③については、記述の通りです。このあたりまで気にするのなら、繰上げ支給をおこなうと寡婦年金の受給権や障害基礎年金の受給権(第2号被保険者である場合を除く)を失うこともあわせておさえておきましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 ~パーソナルプランニング~
第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給

解答 ① アクティブ ② 3.0 ③ 高い
投資信託のパフォーマンスに関する問題です。CFP試験や1級FP技能士試験では、シャープレシオに関する問題はよく出題されますが、2級FP技能士試験で出題とは・・・。ちょっと、厳しいですね。シャープレシオとは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標で、ポートフォリオのパフォーマンス評価に良く用いられます。計算式は、
シャープレシオ = (ポートフォリオの収益率-無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差
ですから、この問題の場合、ポートフォリオの部分を、X投資信託、Y投資信託に置き換えて計算すればOKです。この計算式まで、しっかり頭に入れていた方は、立派ですが、ここまで学習されていなかった方でも、最低限①の問いだけは、正解しないと駄目ですよ。
● 計算過程
X投資信託のシャープレシオ = (10-1)/3 = 3
Y投資信託のシャープレシオ = (13-1)/6 = 2
よって、X投資信託の法がシャープレシオの値は高い。

解答 ① × ② ○ ③ ○
株式投資信託の費用に関する問題です。おっと、メルマガで試験前におこなっている直撃予想(第300回 直撃予想 金融編 昼の部)にて、予想した出題ポイント 「投資信託のコスト」について、ここで、がっつり出題ですね!特に、ひねりもありませんし、これは全問正解したい問題です。販売手数料は、販売会社がお客さんからもらうのですよ。ついでに、販売手数料は、金融機関ごとに異なることも覚えておきましょう。信託報酬・信託財産留保額については、記述の通りですが、この問いとなっている部分以外にも投資信託のコストに関する出題ポイントはありますから、このあたりに自信のない方は、2級FP技能士無料ポイント講座もあわせてチェックしておいてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~金融~
第11回 投資信託にかかるコスト

解答 140000円
投資信託から受け取る税引き後の受け取り分配金に関する問題です。問題を読んだ段階で、特別分配金とすぐに思い浮かべば、GOOD。あとは、計算ミスさえしないように気をつければ、正解できますね。特別分配金がよくわからない方は、「税金は、利益に対してかかる」という大原則に沿って考えてみてください。
分配金を支払う前は、基準価格12000円でしたが、分配金を支払ったことにより、この投資信託の基準価は、
12000円-1500円=10500円となります。
Aさんは、この投資信託を11000円で購入しているわけですから、1500円の分配金を受け取ったものの、ほんとうの儲けは、1000円ですね。
つまり、この1000円に対してのみ、税金が課せられることになりますから、1000円×10%=100円を手取り金額から、差し引く必要があるのです。
というわけで、1500円-100円=1400円
これが100口あるので、受け取る税引き後の受け取り分配金の総額は、14万円となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~金融~
第12回 投資信託にかかる税金

解答 ① 3月15日 ② 650 ③ 更正
青色申告に関する問題です。青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けた者が税務上の特典を受けることのできる制度でしたね。承認をうける期限は、原則として、承認を受けようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となっています。最も代表的な特典としては、問題にある青色申告特別控除があげられます。この金額はFP試験対策として、必ずおさえておきましょう。最高額は65万円です。ここまでは、正解できた方も多いと思いますが、③は、ちょっと難しいというか、何考えてんだか?と言う問題です。更正とは、「税金が間違っていますよ」との税務署からのお知らせ。青色申告者には、その理由を付記することになっているのです。ま、③については、知らなくても問題なしです。最初の2問だけは、正解できるようにしておいてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第19回 青色申告の概要

解答 ① × ② × ③ ○ ④ ○
前問に引き続き青色申告制度に関する問題です。それほど難易度の高い選択肢はありませんし、これは、できれば、全問正解といきたいところです。選択肢③については、よく出題される質問ですから、解説をよく読んでおいてくださいね。
解説
① 誤りの記述です。これは、利子所得ですね。事業所得とは、原則として、事業を営んでいる人の事業から発生する所得のことをいいます。これは、あきらかに、事業から生じた所得ではないでしょう?
② 誤りの記述です。平成22年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入することができます。ただし、事業年度において年間取得合計額300万円を限度としています。
③ 正しい記述です。青色事業専従者給与の特例を受けた者に、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用は、ありません。問題にはなっていませんが、扶養控除も忘れずに覚えておいてくださいね。
④ 正しい記述です。これを純損失の繰越控除といいます。損失の繰越控除をうけるためには連続して確定申告書を提出する必要があります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第20回 青色事業専従者給与とは?

解答 ① 20100(千円) ② 17600(千円) ③ 1850(千円)
事業所得の計算に関する問題です。一見、簡単と思わせておいて、最後の最後に、オチがあるこの問題。まったく油断もすきもありませんね。でも、これが、FP試験。簡単そうに思えても、細心の注意を払って、解答するようにしましょう。
① 貸付金利子が「業務遂行上の」とありますから、これは、事業所得に該当します。ちなみに、この記述がなければ、雑所得に該当することになります。常に、事業所得となるわけではありませんから、誤解のないように。
② 売り上げ原価+車両の減価償却費+その他必要経費の計算をおこなえば正解できます。個人の場合の法定償却法(届出をおこなわない場合はと言う意味)は、定額法です。実質的には、この知識を持っているか質問している問題ですね。
③ ひっかけ問題っぽい解答です。そのまま、素直に、収入-必要経費の計算をおこなってしまうとアウト。この人の場合は、青色申告特別控除があるので、2010万-1760万-65万 = 185万円が正解となります。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
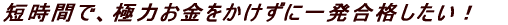
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 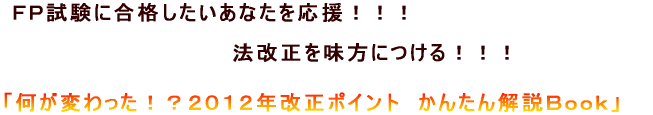
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 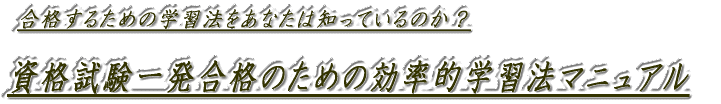
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 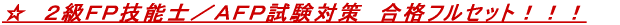 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年-2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
![]()